歯周病の原因を“見える化”する検査
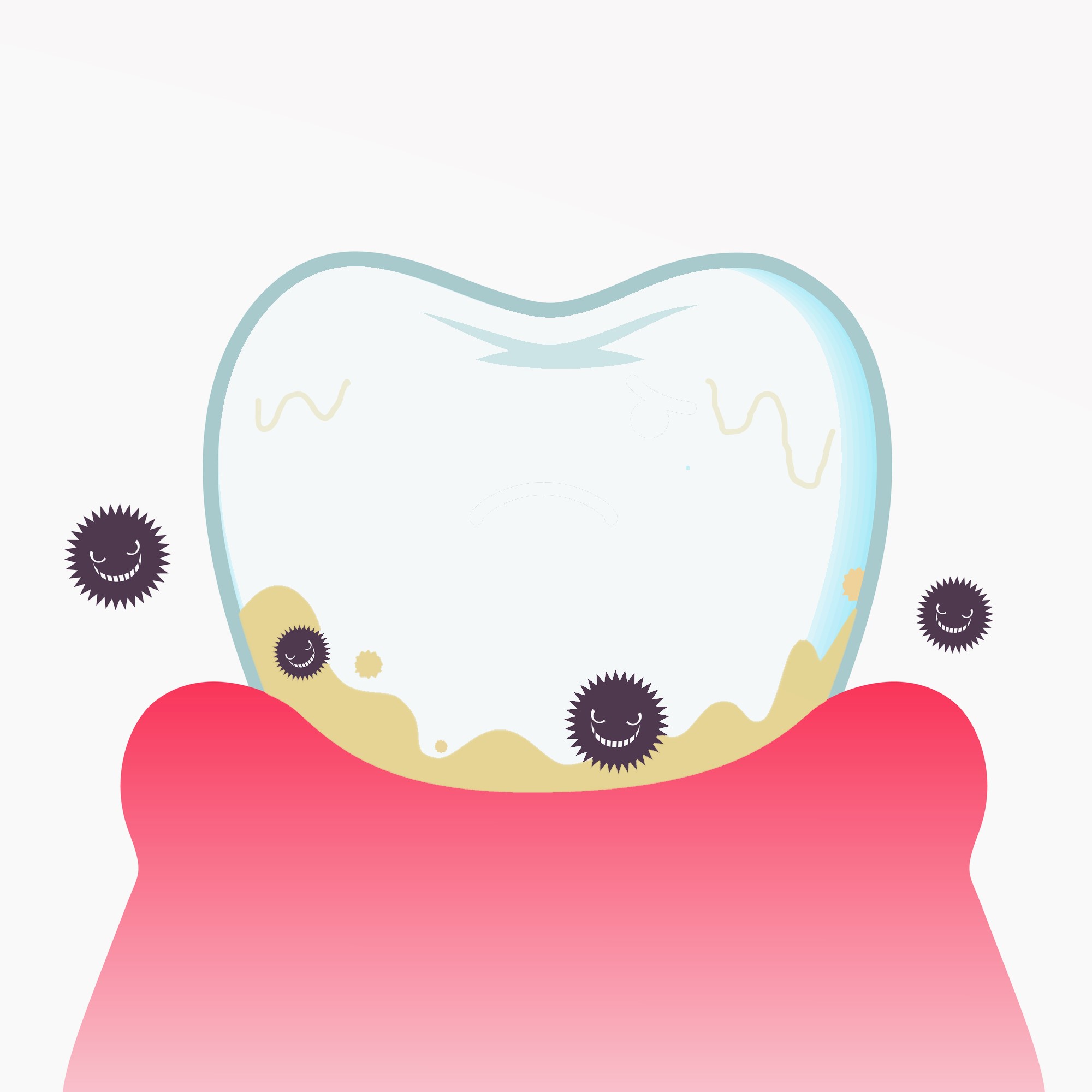 歯周病は「歯の汚れ」だけが原因ではなく、口腔内の細菌バランスが大きく関係しています。
歯周病は「歯の汚れ」だけが原因ではなく、口腔内の細菌バランスが大きく関係しています。
お口の中には500〜700種類もの細菌が存在し、その中には歯ぐきを炎症させたり、骨を溶かしたりする“歯周病菌”も含まれます。健康な状態でも菌は常在していますが、生活習慣の乱れや免疫力の低下などにより菌が増えすぎると、歯周病が発症・進行してしまいます。
そこで当院では、位相差顕微鏡を用いた細菌検査を行っています。お口の中のプラークを採取し、実際にどのような菌が活動しているかを映像で確認することで、肉眼では見えない感染のリスクを“見える化”できます。早期発見・早期対策につながる大切な検査です。
このような症状のある方はご相談ください
- 歯を磨くと歯ぐきから血が出る
- 歯ぐきがむずむずする、または腫れている
- 口臭が気になる
- 歯がグラついている
- 口の中がネバネバする
- 冷たい水がしみる
これらは歯周病のサインかもしれません。気になる症状がある方は、お早めにご相談ください。
位相差顕微鏡検査とは?
お口の中の細菌を“見える化”し、歯周病リスクを把握
 当院では位相差顕微鏡による細菌検査を実施しております。
当院では位相差顕微鏡による細菌検査を実施しております。
患者さまのお口の中の汚れを少し採取し、顕微鏡で観察することで、現在のお口の中にどのような菌がどのくらいいるのかを確認できます。
この検査により、
「歯周病になりやすいかどうか」
「今はどういう状態なのか」
「今後どのように変化していく可能性があるのか」
といった点を把握することが可能です。
当院では顕微鏡検査の結果をもとに、細菌の種類や量に応じて適切な除菌方法を選択し、患者さまごとに合わせた治療を行います。歯周病を引き起こす細菌は、健康な方のお口の中にも常在しているため、完全にゼロにすることはできません。しかし、その数を可能な限り減らすことで歯周病の進行を抑え、再発を防ぐことにつながります。
位相差顕微鏡の動画
位相差顕微鏡検査をおこなうメリット
1. 目で見てわかる安心感
位相差顕微鏡を使うと、実際に患者さまのお口から採取した汚れの中で動く細菌の様子をモニターに映し出せます。
「自分の口の中にどんな菌がいるのか」を視覚的に確認できるため、歯周病の危険性や治療の必要性を直感的に理解できます。
2. 歯周病のリスクを早期に把握できる
歯ぐきの出血や腫れなどの症状が出る前でも、顕微鏡検査を行うことで菌の状態から歯周病になりやすいかどうかを予測できます。早期にリスクを知ることで、予防的なケアを行うことが可能です。
3. 患者さまごとの状態に応じた治療方針が立てられる
口腔内に存在する細菌の種類や数は人それぞれ異なります。位相差顕微鏡で菌の特徴を把握することで、その患者様に合わせたオーダーメイドの除菌方法や治療プランを立てられます。
4. 治療効果を客観的に確認できる
治療の前後で顕微鏡検査を行えば、細菌の動きや数がどのように変化したかを比較できます。これにより、**「治療がどれくらい効果を発揮しているか」**を患者さま自身が確認でき、モチベーション維持にもつながります。
5. 再発予防に役立つ
歯周病を引き起こす菌は完全にゼロにはできませんが、数を減らし続けることが重要です。定期的に顕微鏡でチェックすることで、菌が増えていないかを確認し、再発防止のための早めのケアにつなげることができます。
位相差顕微鏡検査の流れ
1歯周ポケットから細菌を採取
 歯と歯ぐきの間の溝(歯周ポケット)から、少量の歯垢を採取します。痛みはほとんどありません。採取したものから、どの種類の細菌がどのくらいいるかを確認できます。
歯と歯ぐきの間の溝(歯周ポケット)から、少量の歯垢を採取します。痛みはほとんどありません。採取したものから、どの種類の細菌がどのくらいいるかを確認できます。
2 採取した汚れをプレパラートに置く
採取した歯垢を透明のガラス板(プレパラート)に置き、カバープレートを被せて準備します。これで顕微鏡で観察できる状態になります。
3位相差顕微鏡で菌の動きを観察
 プレパラートを位相差顕微鏡に設置し、顕微鏡に接続されたモニターで細菌の種類や動きをリアルタイムで確認します。観察結果をもとに、歯周病のリスクや今後の予防・治療の必要性を判断し、患者様のお口の状態に合わせた治療計画をご提案します。
プレパラートを位相差顕微鏡に設置し、顕微鏡に接続されたモニターで細菌の種類や動きをリアルタイムで確認します。観察結果をもとに、歯周病のリスクや今後の予防・治療の必要性を判断し、患者様のお口の状態に合わせた治療計画をご提案します。
お口の健康を長く保つために
検査結果をもとに、歯周内科で歯周病の進行を防ぐ
 位相差顕微鏡検査でお口の中の細菌の状態を確認したあとは、必要に応じて歯周内科での治療を受けることができます。
位相差顕微鏡検査でお口の中の細菌の状態を確認したあとは、必要に応じて歯周内科での治療を受けることができます。
当院では、歯周病の原因となる細菌に合わせて薬を用いた治療を行い、進行を抑え、再発を防ぐことを目的としています。検査でお口の状態を把握することで、より効果的な治療や予防につなげることが可能です。
歯を守るためには、検査と治療、そして定期的なチェックの組み合わせが大切です。歯周病が気になる方は、ぜひ歯周内科をご検討ください。





